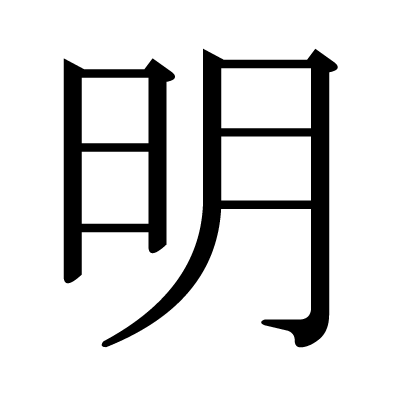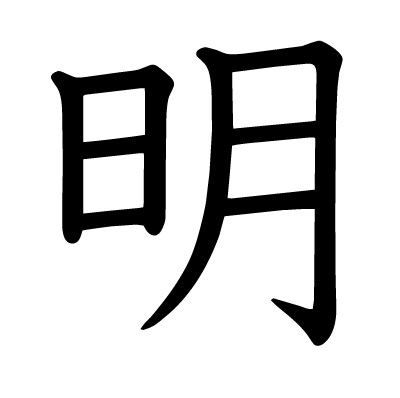漢字「明」について
ふりがな表示

目次
【】明とは?
明は、明るい / 明らか / はっきりしている / 夜が明けるなどの意味を持つ漢字です。
部首は日部に属し、画数は8画、習う学年は小学校2年生、漢字検定の級は9級です。
読み方には、ミョウ / メイ / あ(かす) / あか(らむ) / あ(かり)などがあります。
「明」の基本情報
| 部首 | 日部(ひ・ひへん・にち・にちへん) |
|---|---|
| 画数 | 8画(日4+4) |
| 音読み | |
| 訓読み | |
| 意味 | あかるい。光が当たってあかるい。 |
| あきらか。はっきりしている。はっきりわかる。 | |
| あきらかにする。あかす。 | |
| あける。夜があける。日がのぼり、あかるくなる。 | |
| あくる。次の。夜や年があけて次の。 | |
| あかり。光。あかるくするためのもの。 | |
| この世。現在の世。 | |
| 神。例:明神 | |
| みん。王朝の名前。 | |
| 種別 | 教育漢字 / 常用漢字 / 名前に使える漢字 |
| 学年 | 小学校2年生 |
| 漢字検定 | 9級 |
| JIS水準 | 第1水準 |
※Unicodeは文字コード欄に移動しました。
「明」の書体
- 明朝体
- 教科書体
- 教科書体(筆順)
- ゴシック体
- 楷書体
- 行書体
- 草書体
- 隷書体
- 篆書体
クリップボードにコピーしました
NEW漢字練習帳
異体字
異体字とは
異体字とは同じ意味・読み方を持つ字体の異なる字のことです。
※ 「万」-「萬」 「竜」-「龍」 「国」-「國」 など
→異体字とは
文字コード
| Unicode | U+660E |
|---|---|
| JIS X 0213 | 1-44-32(面区点番号) |
| Shift_JIS-2004 | 96BE |
| MJ文字図形名 | MJ013201 |
| MJ013202 | |
| 戸籍統一文字番号 | 155190(MJ013201) |
| 155460(MJ013202) | |
| 住基ネット統一文字コード | J+660E(MJ013201) |
| J+B27F(MJ013202) |
※文字図形(MJ文字図形名)が複数あるため、戸籍統一文字番号・住基ネット統一文字コード欄にはそれぞれに対応するものをカッコ()で表示しています。
検字番号
検字番号とは
検字番号とは、辞書内での漢字の掲載位置を示す番号です。
先頭の字から順に番号が振られているため、検字番号が小さければ前方のページ、検字番号が大きければ後方のページに掲載されていることが分かるため、目的の漢字が掲載されたページにたどり着く上で役立ちます。
検字番号は「漢字番号」「親字番号」などとも呼ばれます。
| 大漢和辞典 | 13805 |
|---|---|
| 日本語漢字辞典 | 4558 |
| 4559 | |
| 新大字典 | 6408 |
| 大字源 | 3831 |
| 3832 | |
| 大漢語林 | 4455 |
漢字構成
「明」を含む漢字
常用漢字表付表の語
明日(あす)
…小学校で習う語
難読読み
- 明後日(あさって)
人名読み・名のり(名前での読み)
- あきら
- あけ
- てる
- はる
- ひろ